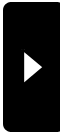2019年07月07日
宇治で玉露席
Tea ceremony 京都、宇治茶の本場でプライベートお茶会体験(玉露席) — Airbnbの体験 https://abnb.me/oSnAtV6z7X
宇治橋側で お茶席体験してます。完全予約です。英語対応です。
宇治橋側で お茶席体験してます。完全予約です。英語対応です。
2019年06月30日
茶会の花
明日のお客様用の 祇園守りが咲いてくれました。室内で咲いたので痛みがなく明日活躍してくれそうです。
竹の花入れに。
竹の花入れに。

2015年05月21日
美の壺
今日、NHKの美の壺の再放送があります。
先日、見逃したので今日こそは!
テーマは「急須」です。
私たちが寶瓶と呼ぶ持ち手なしの
急須は、朝日焼きが作られるものが
宇治の玉露を入れるのに
一番です。
茶師さんたちも使ってられることがあります。
朝日焼きに撮影取材が入り、
お茶席を撮られるのに協力しました。
二條流の茶席を作り
その様子を3時間強撮影されました。
その折の映像が
最後の5分の中に出ます。
私は、お客様役で、次席にいます。
小さな、煎茶茶碗で、5人いっせいに
飲むところが出たようです。
みてください。
先日、見逃したので今日こそは!
テーマは「急須」です。
私たちが寶瓶と呼ぶ持ち手なしの
急須は、朝日焼きが作られるものが
宇治の玉露を入れるのに
一番です。
茶師さんたちも使ってられることがあります。
朝日焼きに撮影取材が入り、
お茶席を撮られるのに協力しました。
二條流の茶席を作り
その様子を3時間強撮影されました。
その折の映像が
最後の5分の中に出ます。
私は、お客様役で、次席にいます。
小さな、煎茶茶碗で、5人いっせいに
飲むところが出たようです。
みてください。
2015年01月06日
初摘み茶会のこと
毎年、宇治福寿園の茶寮では、その年の初摘みのお茶を
もんで、煎茶席を持ちます。
社長夫妻が、お客様を呼ばれて、お茶をふるまわれます。
お菓子も菓寮で、干支菓子をつくります。

今年はじょうよ饅頭で、これでした。
中は、うじのみどりと同じ抹茶あんと白あんです。
朝からつんだお茶が、できあがるのを1時過ぎから市木社中が
集まって待ちます。

市木先生と私と妹弟子のMさんです。
私の着物は、附下です。
おふたりは、訪問着。
やっぱりお正月は着物です。
» 続きを読む
もんで、煎茶席を持ちます。
社長夫妻が、お客様を呼ばれて、お茶をふるまわれます。
お菓子も菓寮で、干支菓子をつくります。

今年はじょうよ饅頭で、これでした。
中は、うじのみどりと同じ抹茶あんと白あんです。
朝からつんだお茶が、できあがるのを1時過ぎから市木社中が
集まって待ちます。

市木先生と私と妹弟子のMさんです。
私の着物は、附下です。
おふたりは、訪問着。
やっぱりお正月は着物です。
» 続きを読む
2014年10月20日
お茶会風景

昨日の二条流の秋の大きなお茶会での写真です。
お水屋、17人がかかって、お点前、お童子、お運び、が
市木先生の後見(席主)をささえます。
お菓子をだしていることろです。
煎茶では、お菓子はお茶とお茶の間に食べますが、
まず、出して取回していただきます。

お茶は、今回は、天目という蓋と天目台があるもので、
文人茶というより、えらい方(お寺さんなど)に差し上げる
フォーマルなものです。
水屋は
» 続きを読む
2014年09月28日
蕪村
 今日のお茶席のかけもの♪
今日のお茶席のかけもの♪花は、まゆみ の一種で、さがり花です。
盛り物は、からすうりとあけび。
寒山十とく がテーマで、
塵取りです。
お煎茶道ですので、
こんなしつらえがされていました。
悲田院でのお席です。
2014年05月07日
昨日のお菓子
 細胞?
細胞?昨夜のNature in Tokyoの写真展に協賛の
老松系 弘道館での夜の茶会のお菓子です。
テーマは「ケの中の聖と俗」
席主は・・・太田達
まぁ、ティーセレモニーです。。。
連休の最後の夜
連休はいつも仕事がらみで外出はしません。
弘道館から案内が間際に来て、魔が差してゆきました。
一人で行きました。ケということやので、
遠目には紬とは見えない、かた物を着て、
前と後ろ肩、一面に藤の花の刺繍がしてあって
着る季節が難しい着物です。
暗闇の待合で、待って、
イベント風な人たちがほとんどです。
「しもたかなぁ。。。。」
あんのじょう、
小保方さんのような恰好のお運びが数人。
白衣姿の太田氏。
というわけで、 » 続きを読む
2014年04月18日
卓上点前
自宅で、お客様を
普通の和室で、お煎茶をさしあげるのに
便利なお点前です。
座卓の上に褥を半分サイズでひいて
盆を置き、茶器をそなえつけます。
畳の上に炉や、建水、水注をならべます。
我が家にはカルフォルニアに日系の親戚が
ひとかたまり・・・います。
50人くらいと聞いています。
若狭藩から、明治維新で思い切って
海をわたった一族です。
ガーデナーからカーネーションの栽培で
成功して一家をなしています。
4世が、結婚をして
一か月日本にハネムーン
そこで、京都を訪ねてきました。
宇治川の観光か、家での茶席か・・・と
ききましたら・・・茶席と。
そこで、無地のひとつもんに着かえて、努めているところです。
アーティストで、喜んでくれました。 » 続きを読む
2013年07月13日
朝茶事が昼へ
来月は橋本妙さんの料理教室もお休み。
7月は小さなイベントで、茶会じたてでした。
写真は、左 橋本関雪記念館館長の橋本妙さん。
毎月1回の料理教室(勉強会?)を心をこめて
開いていくださいます。
右の手元から襦袢が出ているのが・・・私。
7月10日水曜日(だいたい第3水曜午前)
朝茶事のはずが・・・正午に。
お茶が先で、懐石はあと・・・・となりました。
おおいそぎで、琉球を着てかけつけましたが、
絹の織に絽の襦袢が合わずに
手元から出ています。
両方、手縫いのお仕立てです。サイズが
間違っていたのではないのです。。。:0;)
・・・・・夏は麻の襦袢がいるようです。
間に空気が入って浮きます。
着物初心者で、やってみては
失敗して直しながら進んでおります。
もちろん、お茶事に・・・織はX らしいですが、
誰も、おこらはらしません。
夏に着物きただけで、ほめてもらってます。。。。
さて、肝心の料理は・・・ » 続きを読む
タグ :橋本関雪記念館
2013年02月26日
聖母煎茶道教室卒業茶会
毎年、2月末の日曜日、
丸山公園の「長楽館」で、
聖母女子短大の煎茶教室の卒業茶会開かれます。
たいてい、まいります。
方円流の松田秋園先生のお教室は、
光泉洞近くの御池通にもあります。
振袖の生徒さんのお手前が素敵です。
この写真は3階の日本間での玉露席です。
茶会のテーマは、「売茶翁」です。
この掛物は、若沖の写しですが、中谷先生の肉筆。
気楽にお茶を振り売りしている翁。 » 続きを読む
2012年04月19日
2011年11月04日
上﨟ほととぎす
2011年05月02日
弘道館にカフェが!
2011年02月24日
立礼席
橋本妙料理教室で、使うお部屋の
お茶の立礼席です。
後ろの「心」の字は月心寺の尼様の字。
この釜を使って
中式のお煎茶もいたします。
中式はお湯をたくさん、しかも
土瓶から、どぼどぼ・・使うので、
塗にあまりお湯がかからないように・・・
茶盤でざくざく淹れているので
なれません。
でも、炭で沸かしたお湯は
お茶葉の味も2味ほどあげてくれます。
3月16日にはこちらでまた、お茶を一服
煎じる予定です。
2010年06月30日
水無月
2010年05月26日
富春館
5月の半ばに九州へ一泊旅行をして、
大分県の戸次というところに行きました。
その中戸次に大きな庄屋屋敷が残っていて、
酒蔵だった建物も、母屋も
ともに、公開してられます。
そちらで、美風流という奈良の
煎茶のお家元がお点前をしてくださいました。
» 続きを読む
2010年04月07日
榊せい子先生の桜茶会@名張
榊先生のおけいこのお部屋のしつらえです。
「花あるときは、花に酔い・・・」のおじく。
今日は、三重の菖蒲池にある榊先生のお宅で
「桜の茶会」があり、うかがってきました。
茶懐石の先生で、材料から手塩にかけて
すばらしいお料理を作ってくださいます。
それに加えて・・・
書家とお茶人さんであるご両親が
集められたお道具。
せい子先生がとりあわされる妙。
言葉に尽くせぬ贅沢です。
» 続きを読む
2009年11月20日
11月の茶会@ちおん舎
今日は、吉田銘茶園主催の茶会の共催で、
朝から「ちおん舎」さんへ。
三条衣棚上がる西。
鶴田さんの絵のギャラリーも併設。
にじり口からの4畳半の本格的なお茶室を持つ京町家。
この坪庭の先が茶室。
こちらで、薄茶席
吉田銘茶の宇治の茶園でとれた
テン茶を挽いたもの。。
夏を越して味の乗った茶。
そのあと、大広間で
» 続きを読む
2009年06月26日
野むら山荘お茶会終わりました。
英語サークルのメンバーを主なお客様に
23名の茶会を終えました。
薄茶席2席
中式 2席
写真は肝心なところは撮れておりません。
席主をしたり、会計をしたり・・・ばたばたと。
お茶箱の茶席をいたしました。
溜塗の扇面の茶箱でお珍しいものでした。
炉は中式を使いました。
写真がその土瓶と炉(七宝)です。
» 続きを読む