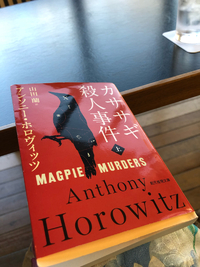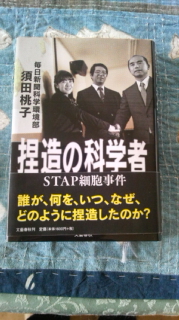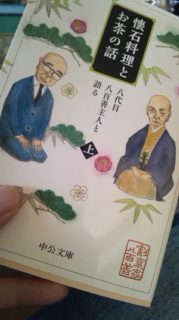2008年05月15日
本の事など
 昨日のお好み焼きの梅田からのブログが
昨日のお好み焼きの梅田からのブログが結構皆さんに見に来ていただいたのが、ちょっと意外でした。
携帯メールは苦手で、いまだに上手に記事を作れません。
ゲストブログお隣の若村さんが、いつもきれいに綴ってられるのを
うらやましくも魔法を見る思いです。
昨日は梅田の阪急へおかだ美保先生の個展へ
先生の原画を初めてしっかりと見せていただく
チャンスと行ってきました。
「かぜのこふうた」という絵本をあすらん書房から出しておられます。
英米児童文学の縁の名の本屋さんですね。
本と人間とどちらがすきかを迷った事のない
時間をずいぶんと長くすごしました。
迷うまでもなく「本」
人間は動くので、扱いにくいですが
本の中の人格は動きません。
作家も作中人物も・・・。
お話はお話になった時点で止まります。
解釈は時代や文化圏によって変わりますが、
それは、コチラの問題ですから。
伏見の英語サークルのテキストが
Inside Mouse, Outside Mouse
by Lindsay Barrett George です。
現代のアメリカの大型絵本で、
ニューリアリズムの文学の流れにある
アメリカらしい絵本です。
ついでに"Aesop's Fables"も
読んでしまう予定です。
なぜなら、"The Country Mouse and The City Mouse"
が、収録されているので、それが
まぁ、ルーツのひとつといえなくもないので。
ただ、寓話があるルールを説明するstoryであるのに
たいしてアメリカの現代絵本にそれは「ない」です。
まめ知識 イソップはアエソポスと書いて
紀元前のギリシャ付近の奴隷です。
二つの動物やもので、お話が構成されていて、
本人作ばかりではないかもしれませんが200ぐらいあります。
今上映中の映画「大いなる陰謀」のもとタイトルは
"Lions for Lambs" で、イソップの" The Wolf and the Lamb"
や、"The Lion and the Fox" などを思い起こさせます。
何かを、伝えようとする寓話性のある作品です。
しかし、日本の題は・・・なんとかなりませんかしら?
ロバートレッドフォード監督 出演のまっとうな反戦作品ですのに。
昨日、梅田へ行ったおりの往復で
茂木健一郎氏の「欲望する脳」集英社文庫
を読み上げました。
読み終わるのが残念な新書でした。
脳のミラーリングの事や
アインシュタインの「自分自身から解放される」の事や
「はっ」とする事がそれはてんこ盛り。
本そのものは、
孔子の「自分の心の欲するところに従っても
倫理的な規範から逸脱しない70歳」という論語の
一文をテーマにしています。
それは、どういったものなのか?
しかし、孔子さんも紀元前の人ですし、
その頃の70歳とはきっと、現代より
個体として消耗が激しかったはずです。
バイタルにも随分縮小した物質としての
「個人」がいたとしたら、そこから出る欲望も変化している
はずです。
年とともに縮む物体としての人間と
そこから出る欲望の量的な減少
意識を使って、それをどのように収斂させていくかを考えると
いいのでしょうか?これは、私の見解ですが。
論語は15にして学問をこころざし、
30にして立つ、40にして迷わず・・のあれです。
しかし、今読むと、15で学問を志せばいい・・
30で一人前になればいい・・
40にして迷いがなくなればいい・・・
結構、のんびりとしてるやないですか?
このごろの子は10歳くらいで学問こころざして
はったりしませんか?理系とか・・文系とか。
はい、皮肉いってます。。。
30で一人前になればいいっていうのも
思い当たる事がありますし。
Inside Mouse, Outside Mouse
by Lindsay Barrett George です。
現代のアメリカの大型絵本で、
ニューリアリズムの文学の流れにある
アメリカらしい絵本です。
ついでに"Aesop's Fables"も
読んでしまう予定です。
なぜなら、"The Country Mouse and The City Mouse"
が、収録されているので、それが
まぁ、ルーツのひとつといえなくもないので。
ただ、寓話があるルールを説明するstoryであるのに
たいしてアメリカの現代絵本にそれは「ない」です。
まめ知識 イソップはアエソポスと書いて
紀元前のギリシャ付近の奴隷です。
二つの動物やもので、お話が構成されていて、
本人作ばかりではないかもしれませんが200ぐらいあります。
今上映中の映画「大いなる陰謀」のもとタイトルは
"Lions for Lambs" で、イソップの" The Wolf and the Lamb"
や、"The Lion and the Fox" などを思い起こさせます。
何かを、伝えようとする寓話性のある作品です。
しかし、日本の題は・・・なんとかなりませんかしら?
ロバートレッドフォード監督 出演のまっとうな反戦作品ですのに。
昨日、梅田へ行ったおりの往復で
茂木健一郎氏の「欲望する脳」集英社文庫
を読み上げました。
読み終わるのが残念な新書でした。
脳のミラーリングの事や
アインシュタインの「自分自身から解放される」の事や
「はっ」とする事がそれはてんこ盛り。
本そのものは、
孔子の「自分の心の欲するところに従っても
倫理的な規範から逸脱しない70歳」という論語の
一文をテーマにしています。
それは、どういったものなのか?
しかし、孔子さんも紀元前の人ですし、
その頃の70歳とはきっと、現代より
個体として消耗が激しかったはずです。
バイタルにも随分縮小した物質としての
「個人」がいたとしたら、そこから出る欲望も変化している
はずです。
年とともに縮む物体としての人間と
そこから出る欲望の量的な減少
意識を使って、それをどのように収斂させていくかを考えると
いいのでしょうか?これは、私の見解ですが。
論語は15にして学問をこころざし、
30にして立つ、40にして迷わず・・のあれです。
しかし、今読むと、15で学問を志せばいい・・
30で一人前になればいい・・
40にして迷いがなくなればいい・・・
結構、のんびりとしてるやないですか?
このごろの子は10歳くらいで学問こころざして
はったりしませんか?理系とか・・文系とか。
はい、皮肉いってます。。。
30で一人前になればいいっていうのも
思い当たる事がありますし。